就職活動はじめたばかりで、よく分からないので経験者の意見を知りたい。
就職活動にコツってあるの?
この記事では、そんな不安をできるだけなくして、スムーズに就活できるコツをお伝えします。
新卒で100社以上、転職で75社以上受けた私が思ったことを、体験談を交えながらお話しますね。
【2024年就活生向け】就活仲間はつくるな。就活のコツ6選
1. 面接中にであった就活生とは連絡をとりあわない
面接中にはたくさんの就活生と出会います。
その中で、ラインを交換する機会も出てくるかと思います。
しかし、ここで連絡をとり合うのはちょっと待ってください。
それぞれの面接スケジュールは違うので、その分どちらかが先に受かるか落ちます。
あまり見ず知らずの人が自分の行きたかった企業に受かった報告を聞いて、あなたはうれしいでしょうか?
どちらかというと、不安になるはずです。
逆もありえますね。あなたが受かって、相手が落ちてしまった時、なんて声かけますか?
そのように、気まずくなって連絡を取らなくなります。
あいてはあくまでライバルです。不安をおさえようとして群れても、結局就活は一人で行っていくものです。
これが、大学のOBなら別です。OBは、受かったESや面接で聞かれること、仕事内容など詳しく教えてくれるので、どんどんつながりましょう。
採用方法が変わったり、面接内容を忘れるため、OBが若ければ若いほどいいです。
あまり年が離れたOBは、連絡しても意味がないでしょう。その人がどれだけ重役であっても、だからといってあなたを受からせる権限があるわけではありません。
また、説明会に来ている採用担当の方の話を伺ったときに、名刺をもらうことができればチャンスです。
名刺には相手のメールアドレスが必ず乗っているので、説明会のお礼や感想を送りましょう。
できればその当日の夜がいいです。採用担当はたくさんの学生を相手にするので、あまり時間がたつとあなたのことを忘れてしまいます。
この子は丁寧な子だと思われて、採用担当から覚えてもらえるし、実際に面接で会うときに緊張が少し和らぎます。
面接後に、再度お礼とやる気アピールメールを送ると、かなり印象がいいですね。
私はこれを、面接から数日たった後に送りましたが、その次の日に選考に受かった連絡が来ました。
偶然かどうかわかりませんが、採用担当への丁寧なメールが合否を分けた可能性もあるわけです。
2. 面接時には、丸暗記をしない
面接が苦手で、丸暗記をしようとしていませんか?私もよくやっていました。
しかし丸暗記は、一度言葉がつまるとつんでしまいます。
なので、言いたいことを箇条書きにして、それをスラスラ言えるように練習することが大事です。
人は、案外聞いている内容よりも、身ぶり手ぶり、その人の表情や雰囲気を見ています。
どれだけ素晴らしいことを言っていても、表情が固まっていたり、動きに違和感があるとそちらばかり気になって、話の内容が入ってきません。
あなたは、面接官が話している内容を覚えていますか?ほとんどの人は、緊張で覚えていないはずです。
相手も一緒なので、内容よりも、それらしくスラスラ言える、優秀な人材を意識しましょう。
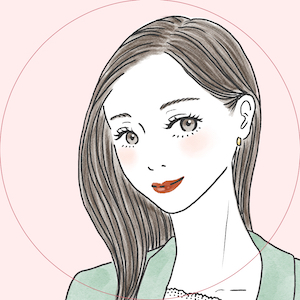
もし言葉に詰まったら?
まだなんとかなります。

「緊張していまして、、」
や「言葉が詰まってしまいすみません」というと、相手も優しく対応してくれます。
面接官も人間ですので、そう言ったやりとりが逆に、「飾らない人物」と高評価になることもあります。
丸暗記は、感情が入りません。すると、全然面接官の心に響かないのですが、言葉のふしぶしに「どうしても言いたいフレーズ」を入れておくと、
「この子は緊張しているけど、しっかりしているな。」となります。
面接は話す内容よりも、態度や感情がこもっているか、視覚聴覚などでうったえていきましょう。
3. みんしゅうは見ない
みんしゅうをご存知でしょうか?企業に受かった人の採用時の質問などを知れる掲示板です。
一見参考になりそうですが、見るのはやめましょう。なぜなら、大体が、受かったことアピールや、推薦で楽に通りましたアピールだからです。
受かった就活生は、あなたとは全く違う大学、専攻、人柄です。その人たちの声は、ほとんど参考になりません。
むしろ、受かったアピールばかりあって、逆に焦ったり、「○日たっても連絡が来ません。落ちましたかね・・・」といった内容も多く、ただ不安をかきたてるだけです。
就活中はただでさえお祈りメールがたくさん届くので、メンタルの維持が不可欠です。
情報が手に入りやすい今だからこそ、あえて見ないようにすることは大事です。
4. 選考がたくさんあっても、一番大事なのは個人面接一択
選考には、ESなどの書類やテスト。面接にはグループ面接・プレゼン面接・ディスカッションなどがありますよね。
この中で一番重要なのは個人面接です。
もちろん、書類は大事です。書類が受からないと、次のステージにも立たせてもらえません。
もしあなたが無事に書類に通り、面接が3回ほどあるとします。その中でも、個人面接が最重要視されます。

え、そうなの?
逆に言えば、どれだけテストの結果がよかろうが、ディスカッションがうまく行こうが、プレゼンを完璧にこなそうが関係ありません。
上記がどれだけうまくいっても、結局合否にかかわるのは個人面接なんです。
ここまで言いきるのは、私がなんども個人面接で落とされたからです。どれだけ採用担当と仲良くなろうとも、関係ありません。
他の面接が上手くいって、最終面接まで行けても最終的にはえらい人があなたの合否を決めます。
そこに、今までのプロセスは関係ありません。
しかし、何回も選考に受かって最後に落ちてしまうほど悔しいことはありません。
ここで、最終面接のコツをお伝えします。
5. 最終面接を突破するためには、年上のお偉いさんと話す
最終面接は、一次面接の若い採用担当とはオーラが違います。
その企業の社長や副社長が出てくるため、オーラだけで圧倒されそうな雰囲気です。

ゴクリ
ここを乗り越えるには、かなりの精神力が必要でしょう。
しかし、出来るだけ同じ状況を経験して、慣れておくことが一番です。
具体的には、副社長や社長、取締役が出てきてもビビらない対策が必要です。
周りの大人にロールプレイングをお願いして、擬似面接をしましょう。
おとながいない場合は、YouTubeで検索して、その人に向かってや想像して話しましょう。
人だけではありません。場所も重要です。
最終面接は、社長や副社長室など、厳粛なオーラが放っています。
そういうシーンになれるには、大学教授に質問しにいったりして、えらい人の部屋に入るシミュレーションをしておきましょう。
場に圧倒されると、頭が真っ白になりがちですが、これは慣れしかありません。
どうしても機会がなくても、今はYouTubeで何でも見ることができます。「社長室」などで検索して、雰囲気をイメージしておきましょう。
6. 親の意見は聞かない
最後に、わりと大事なことを言っておきます。
親の意見はほどほどに聞きましょう。
親世代は、面接がほぼなく、ストレートで大企業に入れた時代です。
やる気さえアピールしておけば、すぐ働けました。
なぜなら、高度成長期でモノがどんどん作られ、売れる時代だったからです。
今は違います。就職氷河期や、コロナで内定取り消しなど、就活生には厳しい時代になりました。
親の意見を聞いてしまうと、
「親と比べて自分は何てダメなんだ・・・顔向けできない」
と自信をなくしてしまいます。
また、親の勧める大企業や地元企業ばかり受けて、機会損失になってしまう可能性があります。
あくまで人生の主役は自分。今の時代にあった情報を取り入れることが大切です。
いまは、情報が手に入りやすい時代になったので、有名ではなくても優良な中小企業にたくさんアプローチできます。
そういう優良企業は結果的にやめにくく、幸せな生活が待っていますので、周りの意見に左右されず自分で考えて行動しましょう。
不安は尽きないが、備えることで緊張も減る
企業面接は、どの学生にとっても大変です。
実際に働いたことない企業の自分より年上でえらい人たちに自分の意見を言うのは、とても難しいです。
なぜなら、今までそういう経験がないから。
これを乗り越えるには、慣れしかありません。この記事のコツをつかみながら、何度も面接を経験して、自分なりに上手くいく方法をあみだしてください。
たまに、内定が大量にもらえる人がいますが、そう言う人は気にしないでおきましょう。
あなたとは、生きてきた環境や考え方がまるで違います。なので、あまり参考になりません。
それより、不器用な私が100社以上受けて分かったコツの方が、あなたの手助けになるはずです。
就活は精神面でやられそうになりますが、あまり深く考えずに、冷静にPDCAをしていきましょう。
私は就職活動をがんばるあなたを応援しています!
筆者が実際に使っていた本↓
企業面接は、どの学生にとっても大変です。
実際に働いたことない企業の自分より年上でえらい人たちに自分の意見を言うのは、とても難しいです。
なぜなら、今までそういう経験がないから。
これを乗り越えるには、慣れしかありません。この記事のコツをつかみながら、何度も面接を経験して、自分なりに上手くいく方法をあみだしてください。
たまに、内定が大量にもらえる人がいますが、そう言う人は気にしないでおきましょう。
あなたとは、生きてきた環境や考え方がまるで違います。なので、あまり参考になりません。
それより、不器用な私が100社以上受けて分かったコツの方が、あなたの手助けになるはずです。
就活は精神面でやられそうになりますが、あまり深く考えずに、冷静にPDCAをしていきましょう。
私は就職活動をがんばるあなたを応援しています!
筆者が実際に使っていた本↓






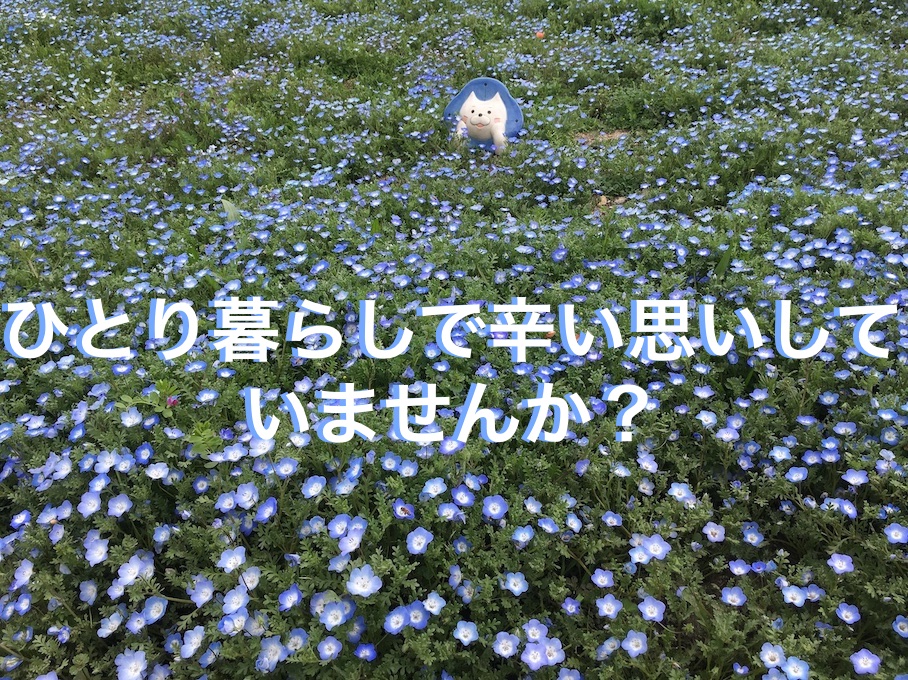

コメント